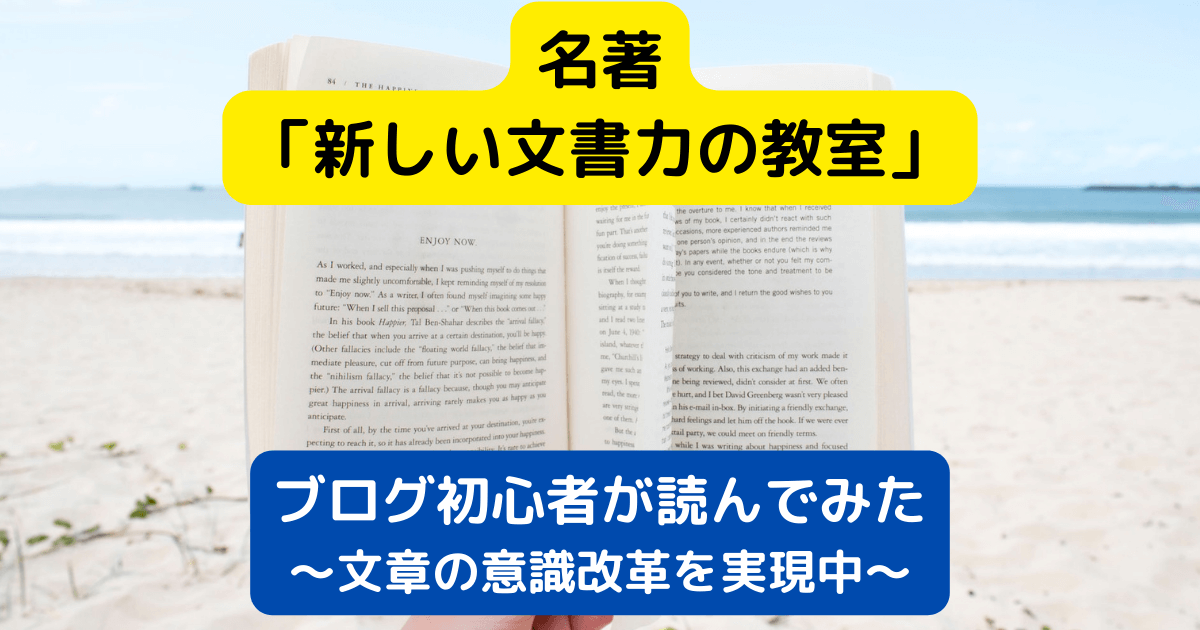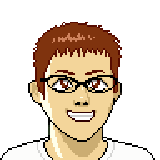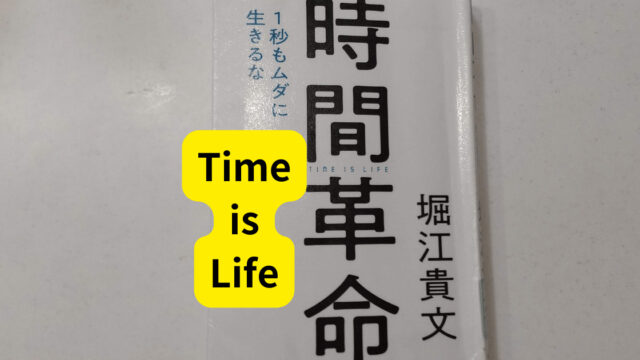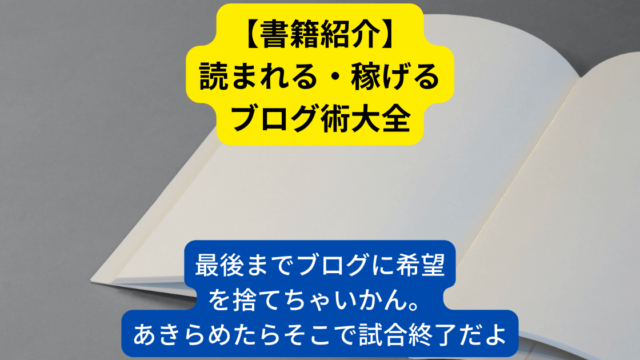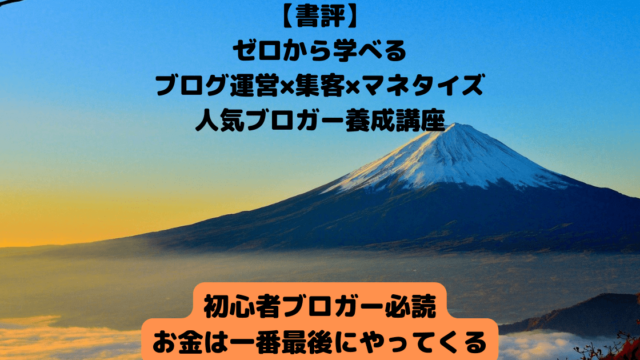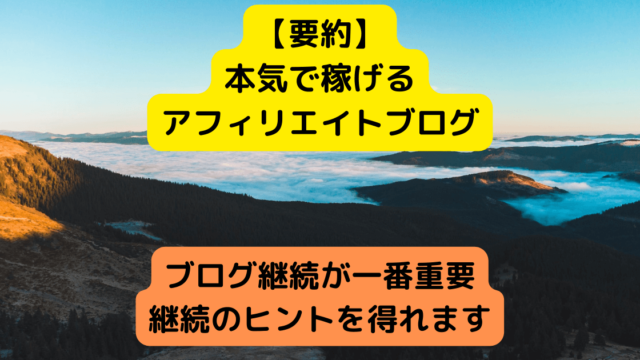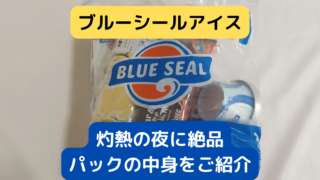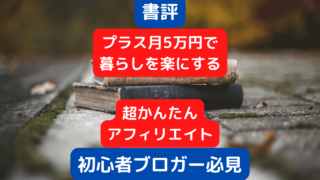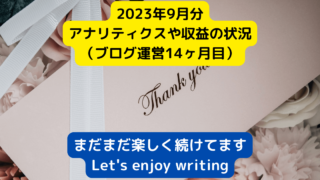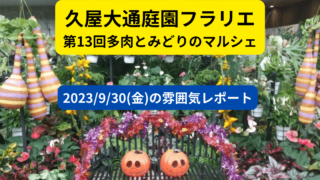おはようございます
サンフランです
先日、名著「新しい文章力の教室」を読みました
「新しい文章力の教室」に出合ったキッカケは、大ファンであるヒトデさん(@hitodeblog)が、「文章を書く全ての人の役に立つ本です」と紹介していたからです!!!
ご参考までに、ヒトデさんが紹介しているブログのサイトは以下です
正直な感想として「新しい文章力の教室」を1回読んだだけでは、理解できませんでした
点と点が繋がってない感じです
3回読み返してみて、少し、理解できるようになってきました
今後も、何度か読み返しながら、理解を深めていく感じかと思います
そんな僕が「新しい文章力の教室」から得たことは以下です
- 良い文章とは「完読される文章」であること
- 文章は「事実」「ロジック」「言葉づかい」で成り立っていること
- サビ頭(冒頭にサビを持ってくる)構成を意識すること
本ブログでは、まだ「新しい文章力の教室」を読んだことのない方に対して、概要や魅力をお伝えさせて頂きます
特に、上記のポイントで記載した内容は、後ほど、詳しくご説明させて頂きます
ブログ初心者の方、絶対に読んだ方が良いです!!!
文章の書き方を学べますし、文章を書くことがもっと好きになる可能性があります
僕は、「新しい文章力の教室」に出合えて良かったと心から思いました
これから、Googleアドセンスに挑戦する方は、こちらもご参考にしてください
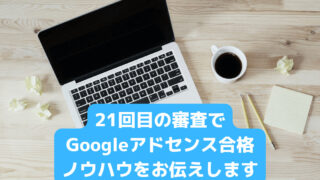
これから、Webマーケティングも学びたい方は、こちらも参考にしてください
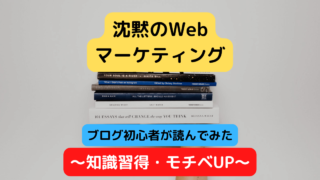
著者について

著者は唐木元(からきげん)さんです
1974年生まれです
2008年に株式会社ナターシャに参加し、編集長として「コミックナタリー」、「おやつナタリー」、「ナタリーストア」を立ち上げました
唐木さんは「唐木ゼミ」と呼ばれる新入社員向けのトレーニングを積み重ねてきました
唐木さんが積み重ねてきたメソッドが「新しい文章力の教室」に凝縮されております
株式会社ナターシャの採用ポリシーは
「書くことはあとからでも教えられるが、好きになることは教えられない」
です
色々な方のブログを見たり、自分自身でブログを書く時点で、「好き」というハードルはクリアしていると思ってます
あとは、「新しい文章力の教室」を読んで、書くことについて学んでいきましょう!!!
「新しい文章力の教室」の構成について

「新しい文章力の教室」は全部で約200ページです
そして、5章構成の中に、77個の文章テクニックが含まれております
各章のタイトルなどは以下です
| 章 | タイトル | テクニック |
|---|---|---|
| 1 | 書く前に準備する | 01~15 |
| 2 | 読み返して直す | 16~29 |
| 3 | もっと明確に | 30~47 |
| 4 | もっとスムーズに | 48~63 |
| 5 | 読んでもらう工夫 | 64~77 |
「これだけのテクニックを駆使しているからこそ、文章は完読されるんだ」
読み終えた時に、こんな納得感を得ることができました(^^♪
あとは、実践で対応できるよう、内容の更なる理解とトライ&エラーを繰り返していきます
「新しい文章力の教室」で得られたこと(5点)

「新しい文章力の教室」を読むことで、様々な知識を得ることができました
その中でも、心に残った5つのポイントをご紹介させて頂きます
あなたも「新しい文章力の教室」を読んで、心に響くポイントを見つけてみてください
①良い文章とは「完読される文章」である(テクニック1)
良い文章とはどんな文章なのか???
このように問われると、色々な回答が思い浮かぶかと思います
この問い対して、「完読される文章」という、明確でシンプルに定義をしているのが大きな特徴です
何だかスッキリしませんか???
僕は、「完読される文章」という定義を聞いて、目の前がクリアになりました
僕は、隔週で図書館へ行き、さまざまなジャンルの本を借りてます
本の中には、「完読できる文章」、「完読できない文章」があります
現在は、「完読できる文章」について、なぜ、完読できたのかを分析してます
当然ながら「新しい文章力の教室」も「完読できる文章」です
完読できた理由を分析してみますと、「もっと上手く文章を書けないか?」という僕の悩みに対して、体験談を踏まえながら、腹落ちするヒントを得られていたからでした
僕は初心者ブロガーとして、日々、記事を書いてます
少しでも、完読して頂ける人が増えるよう、日々、精進していきます
②事実・ロジック・言葉づかいの3層構造(テクニック3)
「文章は、3つのレイヤーで成り立っている。
下から上にかけて、「事実」、「ロジック」、「言葉づかい」という順番である」
上記の文面を読んだときに、衝撃を感じました!!!
このような文章向上を意識してなかったからです
どれだけ美しい文章を書いても、「事実」誤りがあれば、文章として0点です
「ロジック」がおかしな文章は、「言葉づかい」で挽回することはできません
よく考えていると、当たり前のことではあります
ただ、そんな当たり前のことを忘れてしまい、文章として0点となるケースは多々あります
例えば、会社の同僚のメール文章ですと、「事実」誤りのため、0点となる事は多々あります
常に、完読される文章を書き続けるためには、「事実」「ロジック」「言葉づかい」の順に積み上げていく意向を腹の底から理解しておく必要があります
とても貴重な情報でした
これからは「事実」「ロジック」「言葉づかい」を意識して文章を書きます
40歳過ぎても新たな知識を吸収できて幸せです!!!
③基本の構成は「サビ頭」である(テクニック12)
「サビ頭」とは「大事な話題から言う」ことです
つまりは、文章を完読したいと思わせるような、魅力的な一段落を最初に持ってくることが重要です
ご参考までに、「サビ頭」はJ-POPの用語であり、冒頭にサビ(もっとも盛り上がる部分)を持ってくる作曲法のことを指します
例えば、会社のメールでも、結論が最後に書かれているとイライラしませんか(^^♪
知らず知らずのうちに、そのようなメールを書く側になっている時もありますので、気を付ける必要があります
「新しい文章力の教室」を読む前は、最初に結論を持ってきたら、その後の文章が読まれなくなると考えておりました
そうではなく、冒頭で読者の興味を引き付け、関心を引き付けたまま、完読までこぎつけること重要です
これからは勇気をもって「サビ頭」を実行していきます
本当に得ることが沢山あり、幸せです(^^)
④伝聞表現は腰を弱くする(テクニック36)
伝聞表現とは「~とのことだ」、「~らしい」、「~ようだ」という文末の文章のことです
結果として、伝聞表現は説得力がなくなり、信憑性もなくなってしまいます
僕は、これまで、伝聞表現を多用してました
例えば、本ブログや会社のメールなどです
他の媒体から得た情報に対して、断定して表現するのは厚かましい行為だと感じてました(^^♪
「新しい文章力の教室」を読んだことで、裏が取れた事実や取材に基づいた話題は、人づてであろうと断定的に語って良いことが分かりました
そのため、これからは遠慮なく断定的に語り、自信のある文章感を出していきます
当たり前に行っていた文章表現に対して、誤りに気づけた貴重な機会です
自分自身の改善を続けていきます!!!
⑤便利な「こと」「もの」は減らす努力を(テクニック62)
文章で「こと」や「もの」を多用してませんか???
僕は「こと」を多用するクセがあり、ハッと気づくことができました
例えば以下のような例です
【NG】自分のことを理解することで、成長することができるようになる
【OK】自分を理解すれば、成長できるようになる
正直、気を抜くと、「こと」「もの」を使ってしまいます(^^♪
常日頃から「こと」「もの」以外の適切な表現ができないかを考えるクセをつけていきます
僕自身の欠点が見える化できました
ありがたいです
文章力を磨いていきます
さいごに
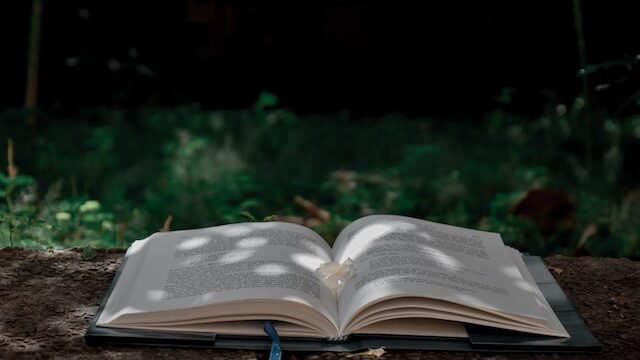
「新しい文章力の教室」は名著であると、心から感じることができました
冒頭に記載しましたが、3回読み返してみて、少し、理解できるようになってきました
僕は、ブロガーとして、まだまだ成長したいです
そのため、たまに「新しい文章力の教室」を読み返すことで、新たな気づきを得て、文章を改善していきます
そして、少しでも多くの方に完読頂けるブログを書いていきます!!!
読書は人生の幅を広げるので良いですね!
ネット閲覧も必要ですが、読書という習慣は続けていきたいと思いました
本ブログでは、引き続き、皆様に有益な情報を発信していきます
では、また!!!